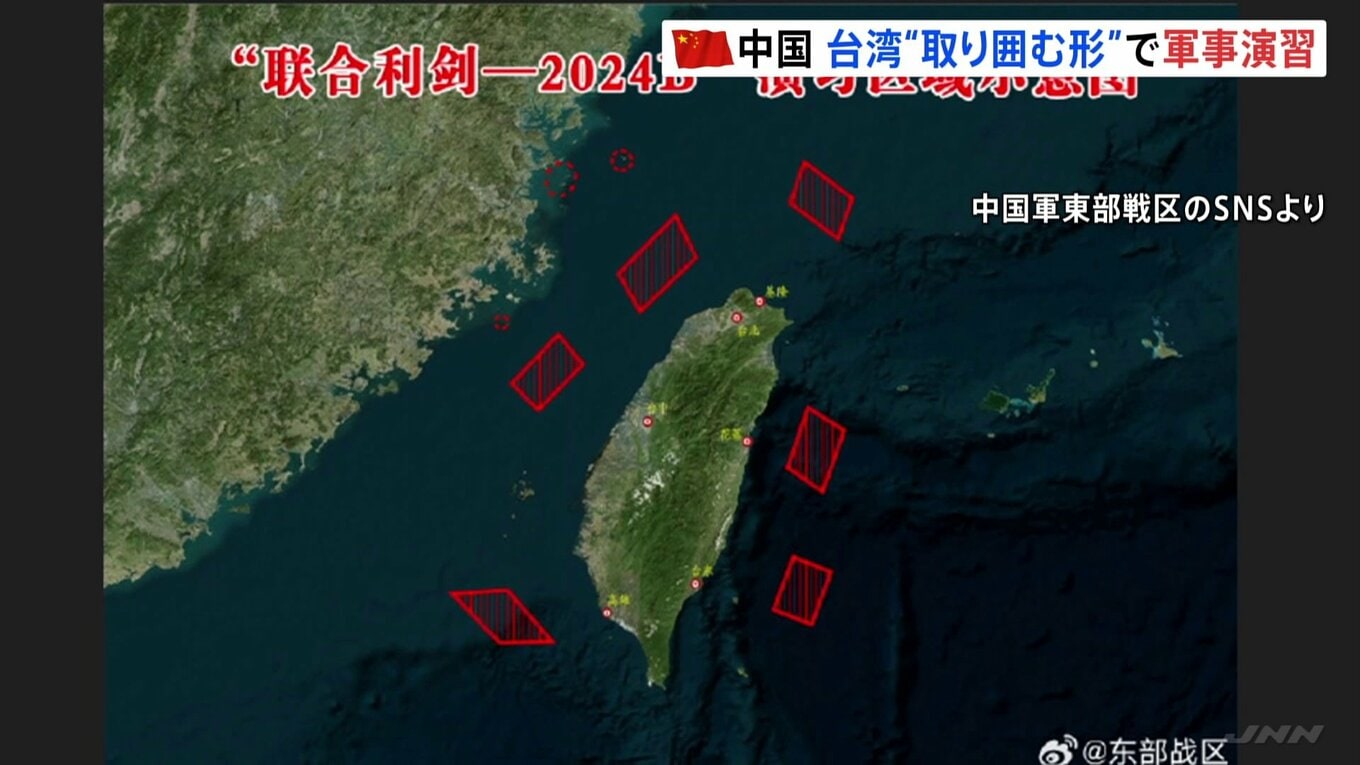中国の軍事史(ちゅうごくのぐんじし)では、中国の歴代王朝の戦争、特に歴史上重要だった民衆反乱や出来事について述べる。主に中国(華夏)と周辺の少数民族、北方の遊牧民族の衝突であるが、アヘン戦争以降は西洋列強の戦争などについても述べる。
ここでは、国家間の戦争や出来事、武器の発展など、軍事史について総合的に述べる。個々の戦闘・合戦については中国の戦闘一覧を参照されたし。ここで取り上げる戦争は中国の歴代王朝の戦争についてのみ取り上げる事に留意。また図表中での攻撃側・防衛側には、発起人や標的となった人物・国を記すため、全貌を示すものでない事に留意。
概説
中国では古来より戦闘が盛んであり、武具の発展も著しいものであった。中国では、黄河文明がシルクロードを経由した鉄器の流入により長江・四川両文明の優位に立ち、殷代の最盛期にはその版図は長江中流域に及んだ。周代には南方に楚国を始めとする諸国が立ち、秦の統一戦争によって、この時代の「中華」が統一された。
漢代には武帝の西域進出によりシルクロードと密接になった中国では、交易が盛んとなりつつあった。しかしその後、漢は崩壊し、三国時代となった。この時代には名軍師として名高い諸葛亮が蜀で奮戦した。その後、屯田制を作った魏から帝位を簒奪した西晋が中華を統一するも、八王の乱と永嘉の乱により短命に終わり、華北には異民族が割拠した(魏晋南北朝時代)。
隋唐時代には様々な制度が整備され、唐はイスラム教徒のアッバース朝と西域を巡ってタラス河畔で激突するも、敗北した。この時に製紙法が西伝していることから、唐代には紙を使った厳格な組織的行動が行われていたことが分かる。しかし安史の乱が起き、中国は再び分裂期に入った。
宋代には武断統治が文治政治に変わり、地方で殆ど独立していた藩鎮勢力を弱体化させた。藩鎮とはそもそも辺境を守る節度使であり、帝権強化のために弱化して禁軍に編入したことが両宋滅亡の原因の一つともされる。その後の元は国内でのジャムチによる移動が可能となり、兵員や物資の効率的輸送が行えるようになった。また南宋で発明された火薬が実用化された。
明代には洪武帝などが北伐を行なったものの、異民族に対して基本的に守勢にあったため、万里の長城が築かれた。現存のもので観光地化されているのは明代のものである。明は満洲地方の女真人に対して兵器や人員の両面において圧倒的優位に立っていたが、李自成の反乱により北京が陥落し、南明政権が立つも、山海関を開放した呉三桂と清の連合軍により滅んだ。
清では八旗制が採られた。八旗には満洲八旗・蒙古八旗・漢軍八旗があり、黎明期の清を支えたが、三藩の乱頃には貴族化しており、代わって緑営が主力となった。乾隆年間に清は最大版図を実現し、十回の征服戦争全てに勝利したということで、「十全老人」と自称する程であった。しかし乾隆帝の譲位以後に政権を握ったヘシェン(和珅)の苛烈な取り立てに反発した民衆らの白蓮教徒の乱頃には弱体化しており、郷勇がこれに代わった。しかしこの後も混乱は続き、華北の捻軍と江南の太平天国が清を脅かした。両者ともに鎮圧されるも、軍閥化した将軍の一人の袁世凱によって辛亥革命が成功し、清朝は滅亡した。
その後を引き継いだ中国国民党は、抗日戦争を2度の国共合作により乗り切るも、中国共産党に大陸の金門地区を除く全てを奪われた。その後、中華人民共和国は、第三世界の一つとして急激に発展し、インド洋・東南アジア地域への展開を進めている。
先秦
先秦時代については、実在性が示せていないものが多く、諸説ある(疑古・信古を参照)。
古国時代においては、黄帝が指南車という道具を用いて蚩尤の撹乱を無効化したとされる(涿鹿の戦い)。この時代には既に青銅器が使用されていたとみられるが、鉄器は出土していない。伝説上では、弓矢を発明したのは黄帝であり、名手であった羿にまつわる多くの話が知られている。
三代においては、二里頭文化圏以降、多くの青銅器が発見されている。夏・殷・周では金属加工技術を独占する傾向があったとされ、この傾向は歴代王朝の弩の製造技術にも見受けられる。
またこの時代は、天体運動や八卦などに頼った戦が主流であったとされる。代表例が殷代によく用いられた亀卜による占いである。しかしその一方で兵器開発も進み、戟という武器が発明され、唐代まで用いられた。
春秋戦国時代
春秋戦国時代の時代区分については、諸説あるが、ここでは西周滅亡から三家分晋までを春秋時代(紀元前771年〜前403年、368年間)、三家分晋から秦朝成立までを戦国時代(紀元前403年〜前221年、182年間)とする。
春秋時代
春秋時代の諸侯間戦争は兵車によるものであった。戦車と呼ぶこともあるが、現代戦車(Tank)との混同を避けるため、以降兵車で統一する。兵車戦は春秋時代の主な戦い方で、趙の武霊王が紀元前307年に胡服騎射を取り入れるまで、騎兵が用いられることは少なかったとされる。また兵車1台あたり、周では75人、楚では150人が付き従ったとされる。また、兵車のみでは戦力にならないため、戈などの近接戦闘具が併用された。
また、春秋時代には弩が発明されたとされる。弩に関する最初の文献的証拠は『孫子』であり、また墨子によると春秋時代に開発されたのは弩や床弩といった、弓矢の発展形の類であったとされる。また紀元前4世紀頃には、弩の機械化も行われていたとされる。また弩兵の戦略的運用に関する記述で、実在性が最も確かな例は馬陵の戦い(紀元前342年)についての記述である。
また、中国の現存最古の兵法書である孫子の兵法が生まれた。これは過去の戦争の謀略を一般的な兵法として反映させたものであり、初歩的な戦争の本質を突いたもので、鬼神や天命観に囚われた従来の兵法を大きく変えたとされる。戦国時代やそれ以後、孫子の兵法の流れをくむものとして、呉子の兵法・司馬法・孫臏の兵法・尉繚子・六韜などが生まれた。
また、諸子百家の様々な思想も兵法に大きく影響を与えた。春秋時代には泓水の戦い(宋襄の仁)のように、戦場でも儀礼を重んじる傾向があったが、後述の戦国時代にはこの傾向が薄れる、または完全に消失することとなる。
戦国時代
戦国時代になると、全高約2.4メートルの攻城弩を始め、雲梯・カタパルト(投石機)などの攻城兵器が発展した。斉の孫臏が戦闘で弩兵を運用している記述があり、既にこの頃には主力の飛び道具として使われていたとされる。
秦代
秦代には既存の長城を繋ぎ合わせ、万里の長城の原型が築かれた。二世皇帝嬴胡亥が宦官趙高の傀儡となり、万里の長城に漆を塗らせようとしたという伝承があるが、当時の万里の長城は高々数メートル程度のもので、明代の長城と比べると、版築を施した馬防柵といったようなものであった。
漢代
前漢時代は、第1次漢匈戦争での敗北と屈辱的講和から始まり、文景の治という安定期を挟み、第2次・第3次漢匈戦争という逆襲の時代であった。内政においては、文景の治末期の呉楚七国の乱により、皇帝への権力集中に成功し、武帝の時期に全盛を迎えた。また財政難解決のため、塩鉄専売制を実施し、郷挙里選の実施により楚漢戦争の元勲らの権力を徹底的に弱めたが、地方の有力豪族の貴族化を招くこととなった。
しかし新の王莽による簒奪によって、武帝の対外膨張政策によって得た領土の維持ができなくなり、長城の一部を放棄することとなった。また、新末後漢初の戦乱により本土は荒れ果て、一時は維持だけで手一杯となった。しかし後漢時代には匈奴側での旱魃を原因として南北匈奴の分裂と南匈奴の服属があり、再興に成功した。また鮮卑の檀石槐も台頭したが、檀石槐の死による瓦解に助けられ、後漢は黄巾の乱まで外戚・宦官・官僚の対立がありつつも何とか持ちこたえた(例:党錮の禁)。
また、漢代には匈奴側でも都市建設が行われており、後の五胡十六国時代の夏が首都とした統万城には甕城の原型とみられるものがあったとされる。攻城戦術も発達し、高い城壁で守った都市に対しては坑道戦が行われることもあった(例:易京の戦い)。
三国時代
三国時代には、河川が国境となったこともあり、水軍が発達した。水軍戦の最たる例が赤壁の戦いである。秦統一までの「中華」である中原地域の魏と河南地域を根拠とする呉・蜀政権の戦いでは、水軍戦に不得手であった魏が大敗し、以降数十年間の国境が確定することとなった。魏は内乱の火種を抱えつつも蜀を滅ぼしたが、内乱を収めた司馬氏による簒奪を受けた。そして後継の西晋が呉を滅ぼし、中華を統一した。
晋代
五胡十六国時代
西晋滅亡後、華北では五胡十六国が華北統一を、江南では東晋が華北奪還を目指した。やがて華北は前秦に統一されるも、淝水の戦いでの敗北をきっかけに分裂し、北魏が再統一を果たした。しかし北魏も漢化政策を始めとする内部対立により東西に分裂、西魏は北周に、東魏は北斉となり、更に北周を継いだ隋が南朝陳を滅ぼし、中華の再統一を果たした。江南ではその間、東晋・南朝宋・斉・梁・陳が交替した。
隋代
隋の楊堅は南朝陳を滅ぼして中華を統一した。しかし618年に江都にて文帝楊堅の次代である煬帝は暴政を理由として司馬徳戡らにより殺害された。楊浩(煬帝の弟の楊俊の子)を擁立して皇帝とし、宇文化及が大丞相となった。その後楊浩を毒殺した宇文化及は許を建国し、隋末唐初が始まった。
唐代
隋末唐初の混乱を平定した唐は、初唐・盛唐期に善政を敷いた。またタラス河畔の戦いではイスラム勢力であるアッバース朝にカスピ海周辺での覇権を奪われるも、安史の乱までは大帝国であった。しかし安史の乱の平定にはウイグルの力を借りねばならず、またこの間に吐蕃に長安を奪われるなどして、唐の権威を失墜させるのに十分なものだった。その後、塩鉄専売制に反発する民衆反乱が相次ぎ、朱全忠による簒奪の後、五代十国時代が始まった。
タラス河畔の戦いをきっかけとして製紙法が西伝しており、このことから戦地では現地生産しなくてはならない程の大量の紙を使用した、緻密な作戦行動が展開されていたとされている。またこの頃に衝車(破城鎚・攻城塔の一種)が用いられ始めたとされる。
五代十国時代
この時代には、唐からの禅譲の流れで繋がる五代と藩鎮系の十国が互いに争った。
宋代
兵器面においては、火薬が発明された。火薬は中国三大発明の1つにも数えられるが、当時は威嚇などに用いただけで、戦闘には用いる形態ではなかった。戦闘に用いるものは南宋時代の実火槍という木製火砲が最初とみられる。しかし南宋時代には火薬は他国に伝わっており、襄陽・樊城の戦いでは、回回砲という大砲が南宋の防衛隊に向けて用いられた。
宋代の主な特徴は、帝権の強化である。唐代では府兵制、後に募兵制が採られたが、節度使の藩鎮化により、唐末には帝国は地方政権と化した。軍人がやがて権力を握るようになり、将軍たちが皇帝を左右するといった状況であった。しかし趙匡胤は、節度使の名誉職化に成功し、兵力は皇帝直属の近衛兵である禁軍に集約されるようになった。その結果として、辺境の防御力が低下し、西夏の独立や遼の侵入を許した。
元代
モンゴル帝国時代には既に回回砲などの大砲が用いられたが、1332年には大元の統治下で、青銅製の砲身長35.3 cm・口径10.5cmの火砲が製造され、元末の農民反乱に対しても多数使用されたとされる。
前身となったモンゴル帝国は侵攻の際、情報戦の一環として、降伏した国家には寛容に接し、抗った国には徹底的残虐を加えた。また商業民と化していたウイグル遺民の協力を得て、西遼滅亡を理由としてナイマンを滅ぼし、版図を拡大していった。南宋に対しても同様の作戦を採り、降将に好待遇で接したため、襄陽・樊城の戦いから臨安陥落までの抵抗はあまり無く、殆ど無傷の江南を手に入れることができた。
元末明初には宋を復興したものとする東系紅巾と徐寿輝の建てた西系紅巾(天完)が現れたが、やがて宋の韓林児を保護した元白蓮教僧の朱元璋が実権を握り、明を建てて漢民族王朝の復興を内外に示した。それに対しモンゴル帝国崩壊後の西半をほぼ統一したティムールは靖難の役の混乱に乗じて永楽帝期の明に侵攻しようとしたが、途中で病死し、帝国は瓦解した。
明代
明は元の技術や交易路を受け継ぎつつ、北伐などを並行して行った。洪武帝は重農主義を採用し、宦官を用いないようにしたが、一方で永楽帝は真逆に宦官を重用して積極的に朝貢体制を敷くことで版図を広げた(例:鄭和の大航海)。そのため、始祖である洪武帝の政策と全盛であった永楽帝の政策の2つで明朝政府は揺れ動き、また皇帝の手足となるはずの官僚が皇帝の猜疑心の強さから事なかれ主義に走ったことからも、政争が絶えなかった。
明の初期は北伐を盛んに行ったが、オイラトのエセン・ハーンが侵入した際、正統帝が親征で大敗して捕虜となった土木の変以後は、長城による防戦一方となった。
火器の運用
明代には永楽帝の治世より滅亡まで、地雷や機雷、火縄槍などが考案された。
他にも火器については紀効新書や練兵実紀など、様々な書物に記された。鄭和の航海では、神火飛鴉(焙烙火矢の原型、火箭)が用いられたとされる記述がある。また、焦勗の書物は火器の製造と使用技術の西への伝播に大きく貢献し、また顧祖禹の地理学は中国の古代から続く兵学の再興をもたらした。
万里の長城
万里の長城は、春秋戦国時代に戦国七雄などが築いた防壁を秦による統一の過程またはその後に始皇帝が連結したものを始めとする、北方の騎馬遊牧民族の侵入を防ぐ防御施設。
秦漢時代の長城は、騎馬遊牧民族から土地を奪ってその優位を保つという観点から、北方の草原に建設された。それに対して隋以後の長城は、隋などの鮮卑系が突厥や柔然に押されていたこともあり、より防衛の色を強めたものとなった。明代の長城に至っては北京から程近い所に築くことで兵員輸送を迅速に行えるようにした。しかし庚戌の変などでは突破され、北京包囲に至ったこともある。
清代
明清交替にあたっては、清は明の兵器技術などを踏襲し、また八旗制や緑営、清朝末期には郷勇など、様々な組織が編み出された。
このような兵制も背景にして、清は旧明領から西方への侵攻を開始した。手始めにグーシ・ハーンの治める青海を(雍正のチベット分割)、そしてチベットや勢力を伸長しつつあったガルダン・ハーンのジュンガルを征服し、これらを自治を認める同君連合に組み入れた。また乾隆帝の治世には、第3次清・ジュンガル戦争以外にも、大小金川の戦い、清・ネパール戦争、大小和卓の乱、林爽文事件、清緬戦争、ドンダーの戦いを戦い、「全て勝った」ということで、自ら十全老人を名乗ったほどであった。しかしアヘン戦争頃になると、兵装は周回遅れのものとなり、南京条約による領土の割譲、日清戦争での敗北以後、列強により瓜分される事態が発生する。これが漢民族による新国家建設運動、辛亥革命の一因となった。
辛亥革命以後
軍閥乱立の国内情勢を北伐によって終結させ中国を統一した中華民国は、さらに日中戦争を連合国による支援と国共合作の元で勝利した。第二次国共内戦にて国民政府を中国共産党が破り、中華人民共和国を建国した後、日中戦争と国共内戦時代の党の私兵集団である紅軍を人民解放軍として再編成し、朝鮮戦争にてアメリカ率いる多国籍軍を撃破して勇名を馳せた。
鄧小平政権時代の軍縮を経て、航空母艦(遼寧・山東)や第5世代ジェット戦闘機(J-20)など現代的ハイテク軍備の導入に踏み切り、軍の現代化を着実に進みつつ、現在は世界第3位の軍事力を保有しているとされる。
脚注
注釈
出典
関連項目
- 中国の戦闘一覧
- 中華人民共和国の軍事
- 中華民国の軍事